多くの業界で必要とされる共通バーコードとして、国際標準のGS1-128が注目されています。利用者は商品や医療機器の管理を正確化し、トレーサビリティの向上を期待できるでしょう。
この記事では、具体的なコードの構造やアプリケーション識別子を使った開発手法などを示します。
– JANやEANなどの他コードとの違いを確認
– AIを使った販売や物流の新システムを把握
– 認識精度向上やRFIDとの比較検討
これらにより、企業や医療機関が効率的にバーコードを管理し、国際規格の要件を満たす可能性が広がります。
今後さらにGTINやQRなど多種類の記号を活用する場合が増えるでしょう。
導入への疑問があれば、当サイト情報を参考に運用方法を検討してみてください。
新バーコードGS1-128の概要と導入メリットをわかりやすく解説
GS1-128はJANやITFだけでは表示しきれない梱包番号やロット番号、重量、請求先企業コードなどの多様な情報をまとめて管理できる国際規格のバーコードです。
この新バーコードを利用すると、食品の賞味期限や医薬品の薬効期限なども同時に表示でき、発注や受発注のデータがスムーズに連動します。例えばEDIと組み合わせることで、オンラインでの受発注から入庫検品までのフローを簡素化し、荷物の出荷先ごとの仕分も効率化できます。
GS1-128をラベルとして導入すれば、企業間で共通の規格を用いた情報交換が可能になり、在庫やトレーサビリティの確認が容易になります
実際の業務ではバーコードリーダーやアプリケーションを活用して、多彩な項目を一元的に管理する事例が広がっています。
GS1-128とは何か?特徴となる国際標準コードの仕組みと利点
GS1-128は国際標準バーコードとしてJANやEANコードの読取り対応を拡張し、公共料金や各種請求の収納もスムーズに行える仕組みがあります。実際にコンビニエンスストアでの払込票に採用され、従来のJANコードから切り替えることで、多様な数字情報を一度に読み取ることができます。
現在、POSシステムでは収納管理が統一され、請求書発行企業とコンビニのデータ連携が正確に行われています。国内では2002年7月以降に段階的に導入が進み、読み取り対応の拡充なども行われています。
GS1-128制定の背景と国際標準化がもたらす業界全体の変化
既存のJANコードやITFは商品を示すには便利ですが、ロット番号や梱包番号、品質保証日などの詳細データは表示することができません。
CODE39のようなバーコードで表現する方法もありますが、企業ごとに定義や桁数がバラバラで、スムーズなデータ交換が難しい状況でした。
GS1-128はこうした問題を解決すべく、国際標準としてデータ項目やバーコードの種類を統一化し、全世界で共通利用できる体制を整えています。
これにより取引先や物流業者との情報共有が円滑になり、業界全体の効率化と発展につながっています。
アプリケーション識別子(AI)の重要性と活用レベルを詳しく紹介
GS1-128で用いられるアプリケーション識別子(AI)は、商品コードや有効期限、ロット番号などのデータ種類を規格化し、正しい桁数や形式で表示する仕組みを支えています。あらかじめ長さが定められた項目と可変長項目があり、シリアル・シッピング・コンテナ・コード(SSCC)や日付情報、ロット番号などが代表的な例です。
メーカーが設定するシリアル番号をAIに組み込むことで、流通や医療、食品分野など幅広い現場で詳細なトレーサビリティを実現できます。統一されたAIを利用すると、複数のアプリケーションやシステムでデータを共有しやすくなり、在庫管理や製造工程の効率化に大きく貢献します。
医療分野でのGS1-128活用事例:医薬品や医療材料の物流管理
医療の現場ではJANやEANコードに加えてGS1-128が導入され、医薬品や医療材料の在庫管理に大きく寄与しています。ロットや有効期限を一括で表示できるため、患者への投与記録や販売包装との整合性をスムーズに確認できます。さらにGS1データバーなどのバーコードとも連携が可能で、医療用医薬品を扱う物流工程の追跡性が高まります。バーコードリーダーの対応次第で多くの医療機器や薬品梱包に応用でき、大幅な業務効率化と安全対策を同時に実現しています。
在庫管理で重要となる新バーコードのトレーサビリティ大きな導入効果
在庫管理では新バーコードGS1-128の活用が広がり、各種データを統合して読み取ることで、入庫や検品、棚卸などの業務負荷を軽減できます。医療用医薬品のケース単位や販売包装、医療機器の梱包など、それぞれに有効期限やロット情報が含まれるため、トレーサビリティの確保が容易です。導入事例では、ハンディターミナルやバーコードスキャナーと連動して実地棚卸を効率化し、人的ミスや読み取りエラーを減らしています。GS1-128で標準化されていることで国際的にも運用しやすく、業種を問わず大きな効果をもたらします。
GS1-128シンボルを実際に活用するための読み取りノウハウ解説
GS1-128シンボルは国際規格のCode128をベースとした可変長バーコードで、JANやITFと異なりアルファベットや記号を含む複数項目をまとめて表示できます。AI(アプリケーション識別子)に沿ってデータを連結し、医療機器や物流単位、食品関係などの幅広い場面で使われています。読む側の機器やソフトウェアが対応していれば、ロット番号や有効期限などの情報を一度に認識し、システムに反映できます。モジュール幅やサイズの調整も可能で、小さな医薬品包装から大きな物流ラベルまで柔軟に対応し、国際的な標準規格に合った運用が可能です。
バーコードスキャナーやハンディターミナルで対応する際の注意点
バーコードには1次元シンボルと2次元シンボルがあり、GS1-128は1次元に該当するため、1次元対応のバーコードリーダーがあれば基本的に読むことができます。もしGS1データマトリックスなどの2次元コードも扱うなら、2次元対応モデルの導入が必要です。また、バーコードリーダーやハンディターミナルごとに対応できるシンボルが異なる場合があるため、購入前にベンダーへ問い合わせて仕様を確認しておくと安心です。読み取るシステムの要件に合わせて適切な機種を選定すれば、現場に合った最適な運用を行うことができます。
読み取りエラーなど起こりやすい問題を減らすための具体的対処策
可変長データを含むGS1-128では、入数や製造ロット番号などの区切りが不明確になる問題が起こりやすいです。この対処としてFNC1という制御コードをデータの末尾に付加し、バーコードリーダーで特定の文字に置き換えて出力する方法が採用されています。可変長項目の終わりを明確に示すことで、連続した数字の途中で読み取りが混乱するリスクが下がります。リーダー機種によってはFNC1を独自の文字に置き換える場合があるため、導入時に設定方法を確認しておくとエラーを最小限に抑えることができます。
物流や公共料金収納など多分野でのGS1-128具体的活用事例紹介
物流に限らず、公共料金や各種料金の収納にもGS1-128は導入が進んでいます。従来はJANシンボルを3段または4段に分けて表示していた料金代理収納の払込票を、1段表示のGS1-128シンボルに切り替えることでデータの読み取りがスムーズになっています。2007年4月以降はこのシステムに統一され、請求書発行企業とCVS等のPOSシステムが共通規格でデータをやり取りできるようになっています。これにより店舗側や利用者側の作業も減り、収納の正確性が増してチェック作業の効率化にも寄与します。今では物流ラベルとの共通運用も視野に入れ、幅広い場面で採用事例が増えています。

公共料金代理収納や物流で自由に使えるGS1-128導入例を解説
公共料金等代理収納のシステムでは、GS1-128シンボルによって複数情報を集約表示し、コンビニエンスストアなどのPOSシステムで円滑に処理できるようにしています。かつてはJANシンボルを複数段で運用していましたが、1段にまとめられることでバーコードリーダーでの読取りが効率化されました。統一システムによって請求書発行企業も新たなバーコード生成方法を取り入れやすく、代理収納に求められるデータ管理がよりシンプルになっています。こうした運用例は物流面でも応用可能で、情報量の多いラベルを1本のバーコードに集約する利点が評価されています。
BarTenderなどラベル作成ソフトを使ったGS1-128バーコード生成法
ラベル作成ソフトを使えば、GTINをはじめ商品識別や製造年月日、有効期限、ロット番号などをまとめて表示するGS1-128バーコードを簡単に作成できます。BarTenderでは「アプリケーション識別子ウィザード」に沿って必要な項目を入力すれば、AIと呼ばれる識別子や桁数を自動調整してバーコードを生成できます。物流や医療、食品など多様な業界で、標準番号管理と合わせてアプリケーションを導入すれば、複数の情報を一括で表示し、業務効率を高めることができます。また、印刷時にバーの大きさやラベルの種類を最適化すれば、読み取り率の向上や作業スピードの改善にもつながります。
| ソフトウェア名 | 開発元 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 適している用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| BarTender | Seagull Scientific | ・多様なバーコード対応 ・データベース連携 ・自動印刷機能 ・複数エディション展開 | ・業界標準として広く認知 ・高度な自動化機能 ・豊富なバーコードライブラリ ・セキュリティ機能が充実 | ・比較的高価 ・小規模利用には機能過剰 ・やや複雑なインターフェース ・初期導入の敷居が高い | ・大規模製造業 ・医薬品業界 ・複雑なラベル要件がある企業 |
| NiceLabel | Loftware | ・クラウド対応 ・直感的なデザイナー ・多言語対応 ・Webベース印刷フォーム | ・モダンなインターフェース ・クラウドベースの柔軟性 ・プリンタ制限がない ・優れたユーザーフォーム機能 | ・サブスクリプション型が主流 ・クラウド版は継続コストが発生 ・一部機能はエンタープライズ版のみ | ・グローバル企業 ・クラウド基盤を活用している企業 ・複数拠点での展開 |
| TEKLYNX | TEKLYNX | ・スケーラブルなソリューション ・様々な業界テンプレート ・データベース接続 ・フォームデザイナー | ・BarTenderより低価格 ・優れたカスタマーサポート ・直感的な操作性 ・業界別テンプレート豊富 | ・エディションによって機能制限 ・自動化機能は上位版のみ ・データベース連携は高度な知識が必要 | ・中小規模の製造業 ・流通/物流業 ・コスト重視の企業 |
| ZebraDesigner | Zebra Technologies | ・Zebraプリンタとの最適化 ・簡易なインターフェース ・基本的なデータベース連携 | ・Zebraプリンタとの互換性が高い ・使いやすく初心者向け ・基本機能に絞った低価格版あり ・インストールが容易 | ・主にZebraプリンタ向け ・他社プリンタとの互換性に制限 ・高度な自動化機能が限定的 ・エンタープライズ機能が少ない | ・Zebraプリンタ使用企業 ・小規模事業者 ・シンプルなラベル要件 |
医療機器や医薬品を含む新バーコードGS1-128関連の最新動向を探る
医療機器では、JANやITFだけでなくGS1-128を利用し、有効期限やロットなどの情報を一括表示する流れが一般的です。包装面積や表示スペースの都合で、1つのGS1-128が長くなる場合は2段バーコードに分割する手法もあります。現在、国内では基本的にGS1-128シンボルを用いつつ、ダイレクトマーキングのようにスペースを確保できない場合などはGS1データマトリックスを活用するケースが増えています。
海外ではGS1データマトリックスの利用が多い一方、日本ではGS1-128が主流です。統一規格を利用することで、医療機関やメーカー同士の情報連携とトレーサビリティがさらに向上し、安全性と効率性を兼ね備えた運用が進んでいます。
海外規格との相違点と国内導入の主要ポイントを正しく押さえる方法
海外ではGS1データマトリックスなど2次元シンボルを活用する事例が多く、バーコードの大きさや読み取り機器の性能も日本とは異なる傾向があります。国内でもGS1-128自体の仕様は国際標準と同じですが、実際の店頭や物流で運用する際は、包装サイズや機器設定など細かい点に注意が必要です。AIの設定や桁数を間違えないように管理ルールを明確にし、運用現場のニーズに合ったバーコード表示を行うことが安定した導入のポイントになります
こうした手順を踏めば、海外仕様との互換性を保ちながら国内での運用をスムーズに進めることができます。
まとめと今後のGS1-128発展に向けたポイントや注意点を総括
GS1-128はJANコードやITFでは表せない製造年月日、梱包番号、品質保証日、発注番号などの情報を国際標準で扱い、さまざまな業界でスムーズなデータ交換を実現します。企業ごとに桁数やバーコード規格が異なると、せっかく表示しても正確な取り引きやトレーサビリティが難しくなります。
GS1-128の導入により、ロット管理や在庫把握、物流段階での分別作業なども一元管理しやすくなるため、業務フローの簡素化やミスの削減が期待できます。さらにバーコードリーダーやハンディターミナルの対応範囲を確認しながら、実際の運用に合わせた導入を進めれば、国際的な流通システムとの連携もスムーズになるでしょう。
バーコードリーダ製品情報
レーザーバーコードリーダー MD210+(USB接続タイプ)


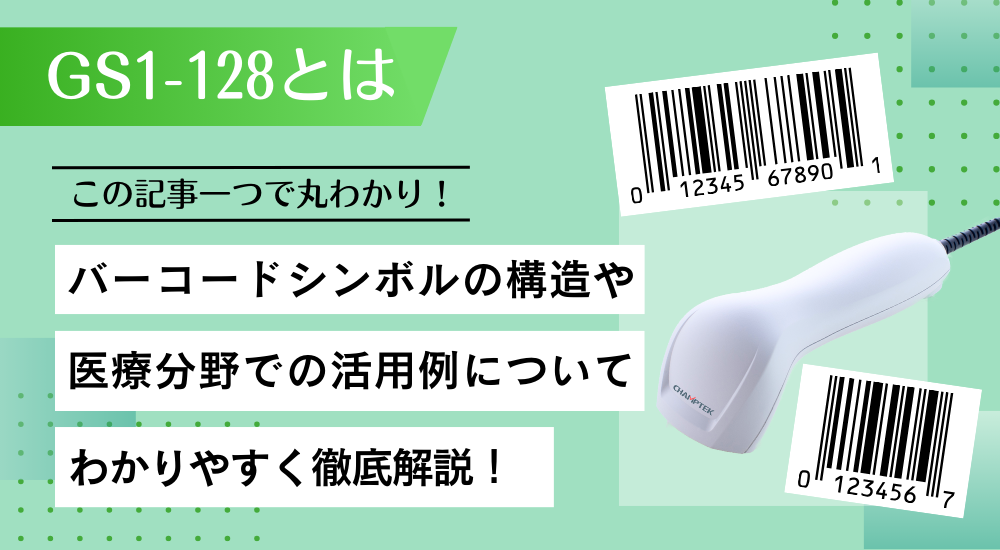

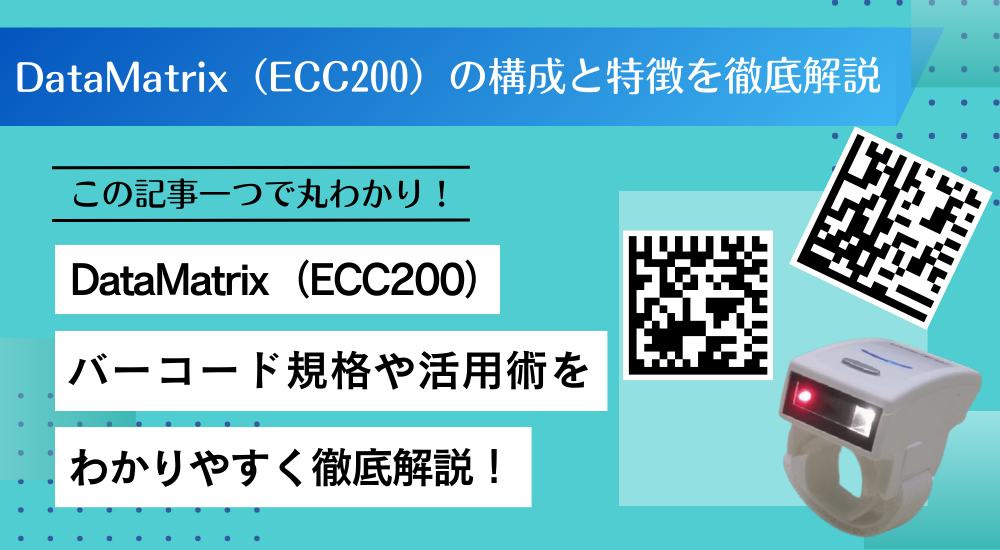
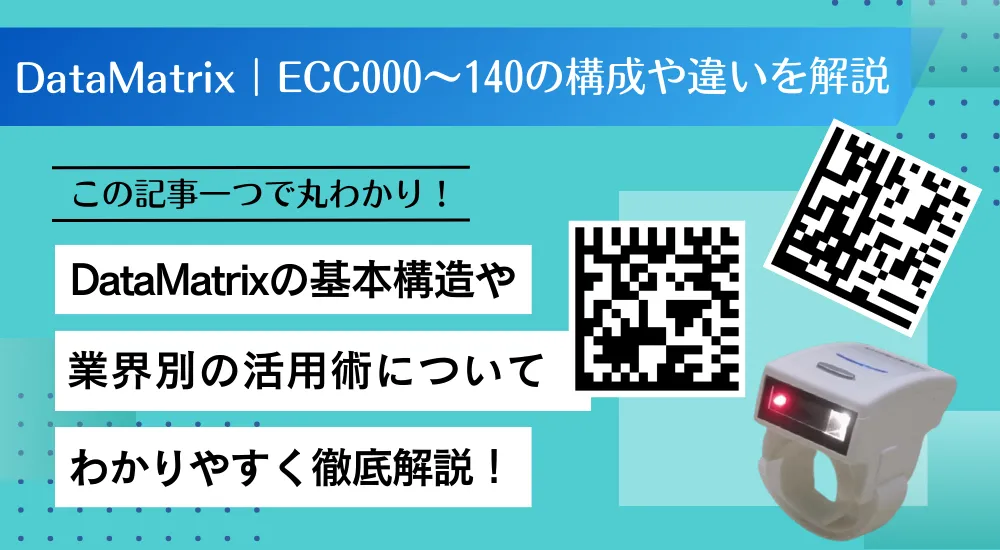
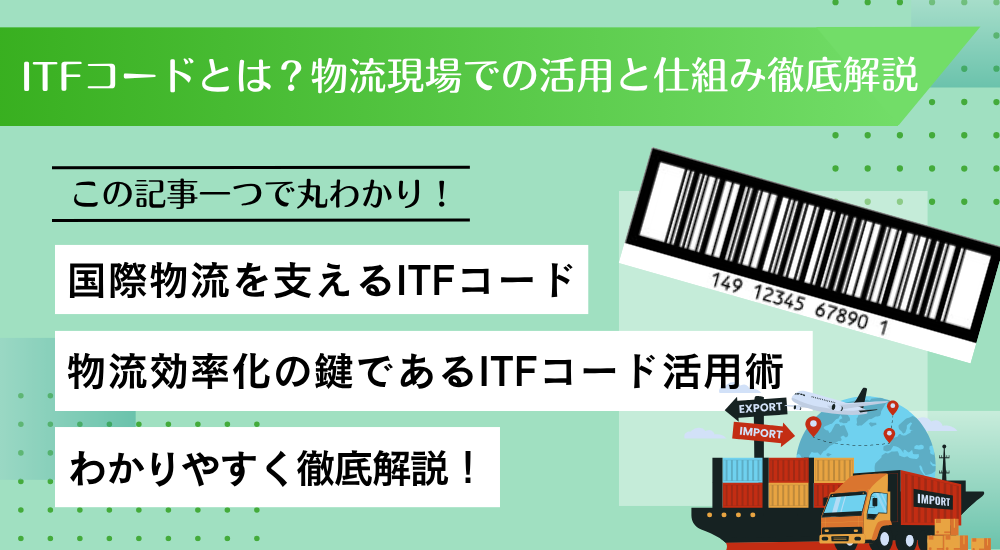


 https://www.nmedia.co.jp/
https://www.nmedia.co.jp/