JANやEANなどの国際標準バーコードはPOSや日本・アメリカ・カナダなどの流通で広く利用され、UPCやITFとの互換性も備えています。
この記事ではGSやチェックデジットを含む番号の構成、Codeの印刷規格、国内で申請する際の注意点などを解説します。
さらに海外商品への活用を参照して、企業や個人が国際的に対応できるバーコードを正しく作成・設定する方法を紹介します。
こうした知識を得ることで、商品を円滑に識別し管理するための仕組みを理解し、必要な場面で円滑に導入することが可能となります。
JAN/EANとは?商品識別に欠かせない国際標準バーコードの概要
JAN/EANは世界の流通やPOSシステムで広く活用されるバーコードで、商品識別において重要な国際標準になっています。各コードには国や企業の識別番号が設定され、最後にチェックデジットが付いています。JANコードは日本向けですが、EANコードがベースになっているため構成方法は同じです。UPCとの互換性もあり、アメリカやカナダなど異なる地域のPOSレジでも基本的に読み取りが可能です。製造業でも在庫管理や物流の効率化を目指す場面で活用しやすく、多くの企業が導入しています。数字の組み合わせが統一されていることで、世界各地の流通システムへ対応しやすいバーコードとして機能します。互換性が高い特徴から、多様な業界で利用され、多国籍企業の商品管理にも役立ちます。国際規格であるため、海外へ販売を検討する際にはJANコードのまま輸出を進められる場面が多く、販売チャネルを広げる一助になります。
JANコードとEANコードの違いは?基礎知識と相互関係を解説
JANコードはJapan Article Numberの略称で、日本国内の流通を中心に利用されています。EANコードはEurope Article Numberとしてヨーロッパをはじめとする各国で使われ、JANとコード体系が共通の仕組みです。国コードを変えるだけで海外での読み取りが可能になり、多くの企業が国際的な商品管理に活用しやすいです。輸出先で別のコードを取得しなくても対応できる場合があり、市場展開を円滑に進めやすいメリットがあります。
JAN/EANコードの基本構造と利用される業界について
JAN/EANコードは標準バージョンと短縮バージョンに分類され、バーコードの左右にガードバー、中央にセンターバーを配置します。数字は企業や商品を示す要素を順番に並べ、最終桁には計算により決定されるチェックデジットが含まれます。製造現場では在庫管理の効率化を図るために活用され、小売店や物流業界でもPOSシステムとの連携が容易です。バーの配置と数字構成が国際規格に基づいているため、多国籍な事業体にも受け入れられ、販売経路を越えた商品データの一元管理に貢献します。
JAN/EANの番号体系を徹底解説!構成と桁数の意味を理解する
JAN/EANは国や企業などの情報を一連の数字で示し、標準と短縮の2種類に大別されます。スタートやストップといった特別な文字は備えず、レフトガードバー・ライトガードバー・センターバーで区切りを示します。12桁の情報と最後のチェックデジットで合計13桁を表す仕組みになっており、バーコードリーダーが読み取る際に誤りを防ぎやすいです。標準バージョンは世界のPOSシステムで扱いやすく、短縮バージョンはスペースが限られた商品への表示に重宝されます。また、どちらも同様のデータを内包できるため、流通業のみならず、製造や物流の現場でもバーコード管理がスムーズに行えます。国際的に統一された体系が整備されていることで、海外への販売を目指す場合もスピーディに導入できる利点があります。
国際共通の商品コードGTINを構成するJAN/EAN番号の詳細
GTINは国際的な商品コード体系を指し、その中核を成すのがJAN/EAN番号です。標準バージョンでは13桁、短縮バージョンでは8桁の情報をバーとスペースで表現し、センターバーを含む独特の構造で判別精度を高めています。JAN/EANはいずれもチェックデジットを組み込むことでデータ誤読を防ぎ、POSや物流など多様なシステムでスムーズに運用可能です。企業ごとの情報が数字に割り当てられるため、国境を超えた商品管理にも適しており、GTINとして統括されることでグローバルな流通にも対応しやすいです。世界中の業界で採用される理由は、単なるバーコード表示にとどまらず、生産から販売までのトレーサビリティを実現できる点にあります。
チェックデジットとは?JAN/EANコード正確性維持のための仕組み
チェックデジットはJAN/EANコードの末尾に付加される数字で、バーコード読み取り時のエラーを極力抑える役割を担います。JANはEANを基に作られており、数字の並びに国や商品の情報が含まれる点は同様です。アメリカやカナダで使われるUPCも互換性があるため、POSレジで共通の商品コードとして扱いやすいです。製造現場や流通業では、この仕組みにより在庫や販売データの正確性を保つことができます。JAN/EANは多種多様な国際市場で利用され、チェックデジットを含む統一ルールがあることで、スムーズに活用できる場面が広がります。
JANシンボルの規格と仕様を理解しバーコード印刷に活かす方法
JANシンボルは13桁または8桁の数字だけで構成され、バーとスペースの幅を変化させることで情報を可視化する規格です。投射光に対する反射率の差を利用するため、黒や白に限定されず、規定の条件を満たせば多様な色調が使えます。印刷時には数字をバーの下部に表示したHRI(目視可能文字)を追加し、読み取り不能な場合に手動で判断できるよう工夫することが望ましいです。バーとスペースを組む最小幅をモジュールと呼び、これを何種類か組み合わせる4値コードとして運用されています。指定された規格と仕様への理解があれば、バーコード印刷で高い読み取り精度が期待でき、商品識別や流通の効率化につながります。
バーコード作成時の注意点とJANコード印刷の基本寸法と倍率
バーコードを作成する際は、13桁目に任意の数字を入れられない点が重要です。そこはチェックデジットであり、1~12桁目から計算した結果を入れないと読み取りエラーになります。さらにJAN-13の先頭に0を付けるとUPC-Aと同じバー構成を持つため、12桁として認識するバーコードリーダーがあります。13桁で読み取りたい場合はリーダーに設定を加える必要があります。こうした仕様を把握して印刷することで、POSシステムや在庫管理の段階で混乱を生じにくくできます。正しい寸法と倍率の選択も大切であり、規格に沿って印刷すれば高精度の読み取りを期待できます。
JANシンボルのバー構成上の特徴と読み取り精度向上のポイント
JANシンボルは13桁または8桁の数字のみを用い、バーとスペースの幅を複数のモジュールで表現します。投射光の反射率差が見分けやすい配色であれば色調への制限は少なく、OCRBフォントなどの目視可能文字を下部に添えることで、機械が読み取れない場合の確認にも役立ちます。1キャラクタを7モジュールで表す4値コードとして設計され、安定した読み取り精度が得られるよう工夫されています。バーの幅やスペースの組み合わせは厳密なルールがあるため、規定通りに作成すればレジやハンディスキャナで誤認識されにくくなります。
日本国内でJANコードを利用するための申請方法と取得手順
日本では1970年代にPOSシステムの試験運用が始まり、流通の効率化を目指してバーコードの統一が検討されました。当初はUPCを参考に複数の候補が挙がりましたが、最終的にUPCと互換性を持つEANシンボルを採用し、これを日本向けに整備したのがJANコードです。1978年にJISとして公示され、国際流通コードの要件を満たす国内標準として普及しました。JANコードを利用するには、所定の団体へ登録申請を行い、企業別に割り振られた企業コードと商品コードを組み合わせた数字の列を管理します。こうして取得したJANシンボルは、売り場や物流システムで読み取りやすく、日本の流通を支える役割を果たしています。
JANコード新規登録申請時に必要な情報と手続きの流れ
新規登録を行う際は会社情報や事業内容、割り当てたい商品コードの範囲などを準備し、所管のGS1関連組織へ申請する流れが一般的です。JANコードはJIS X 0507やISO/IEC 15420で規格化されており、海外規格との互換性も高いです。登録後に付与される企業コードに商品を割り振る形でJAN-13やJAN-8を発行し、バーコードを作成します。さらに目視用の数字表記を含むフォントを選定すれば、POSでの読み取りと目視確認の両面から流通を支えやすくなります。方式を把握し、正しい手順で進めれば国内外の市場で活用できるバーコードとして機能します。
海外商品の識別方法は?アメリカ・カナダ等のJAN/EANの活用
海外へ商品を出荷する際、JANコードは基本的に多くの国際POSレジで読み取りが可能ですが、北米では12桁のUPCが長年使われてきた経緯があるため、旧システムでは13桁のJAN/EANを認識できない場合があります。2005年以降、米国やカナダでも13桁対応が進んでいますが、一部の店舗や事業で古いシステムを使うケースが残っています。輸出時には現地の取引先にJAN/EANの読み取り可否を事前確認し、必要に応じてUPCとして表示するなど対策を検討することでトラブルを防ぎやすくなります。国際流通の基盤としてJAN/EANを活用するには、現地状況を把握しながら確実な商品管理を行う姿勢が大切です。
海外で作成された商品でもJAN/EANコードは使用可能か?
海外で製造された商品でも、JAN/EANコードを適切に割り当てれば日本を含む多くの国や地域で読み取りが行われます。北米へ輸出する場合はUPCとの互換性を踏まえつつ、現地のPOSレジが13桁対応かどうか確認する必要があります。13桁非対応の店舗や事業所が存在する場合、別途UPC表示を検討するとスムーズに流通へ乗せやすくなります。この仕組みを活かして世界中の販売先を見据えるなら、早めの申請や情報収集を進めると役立ちます。ぜひ一度、GS1への登録手続きや現地システムの調整などを確認して、新たな市場展開に生かしてみてください。
この記事についているタグ: # バーコード




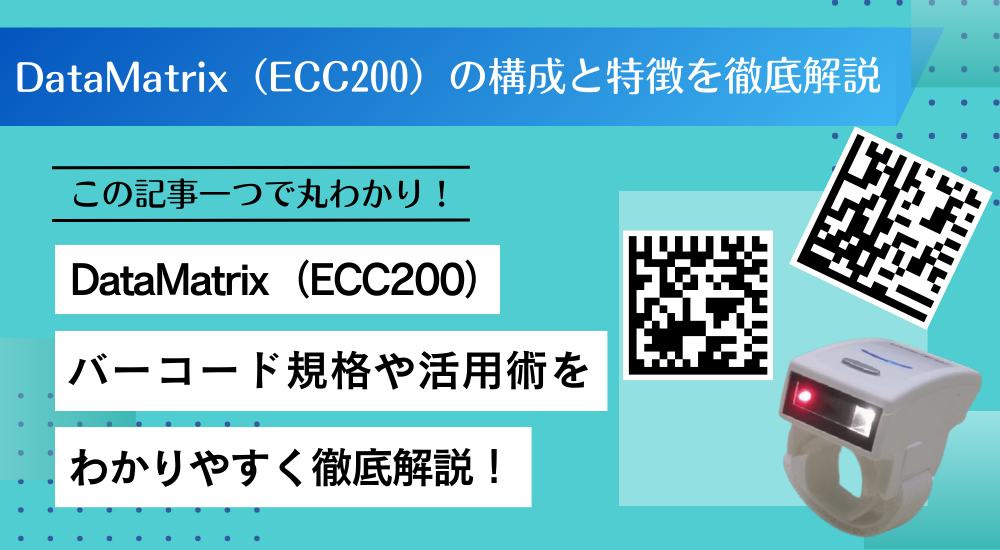
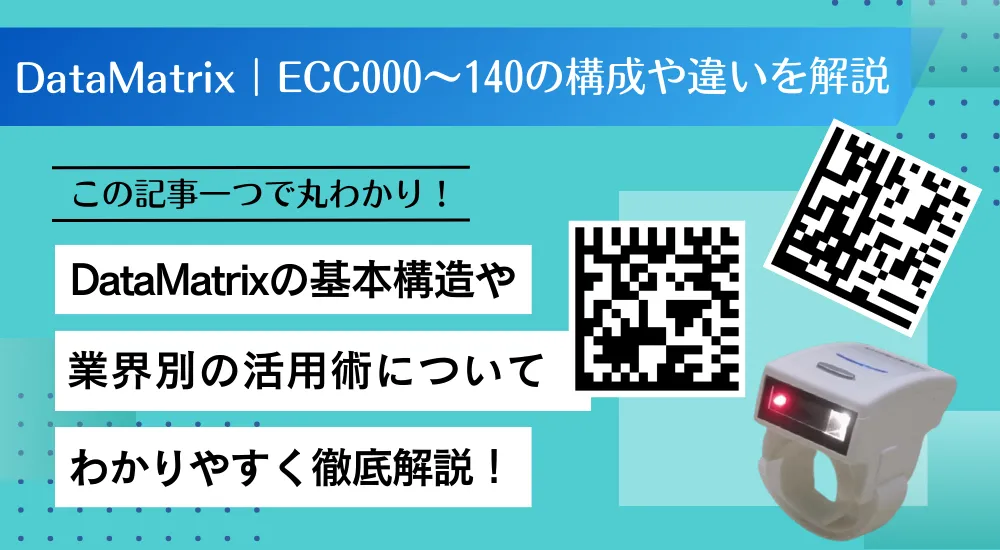
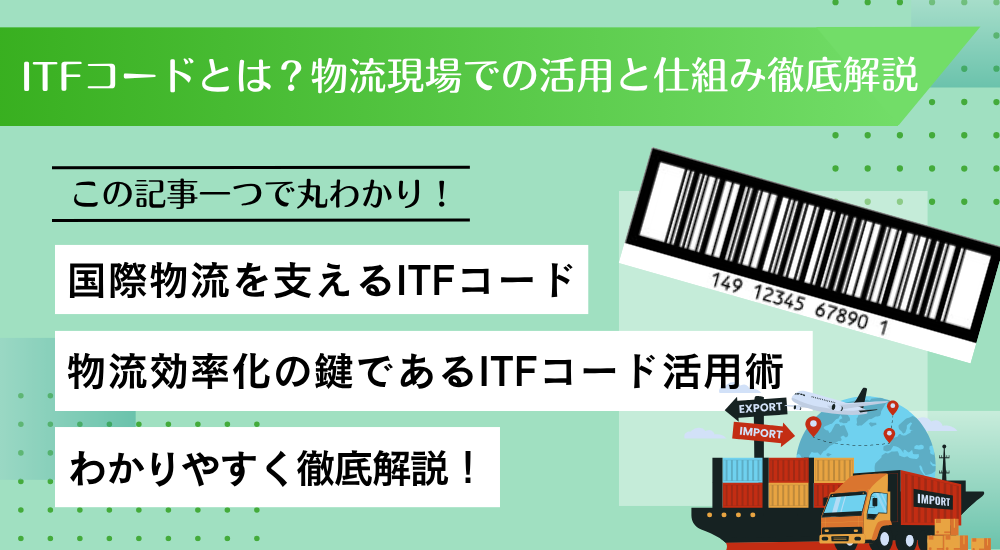


 https://www.nmedia.co.jp/
https://www.nmedia.co.jp/